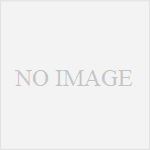昭和30年代ごろまでの住宅は、軒や縁側があり日陰で風通しのよい場所ありました。庭には木が植えられ、垣根もあって夏の日差しと上手な付き合い方ができていました。漫画サザエさん一家の住宅のようなイメージです。
窓も木枠でスキマ風も入り、もちろんエアコンはありませんでした。
窓の役割も、時代に応じて変化しています。風通しをよくするだけで十分だった窓が、快適な室内温度の調整に重要な役割を担うようになっているのです。家は家族が集う場所で、1日のうちでも長い時間を過ごします。夏場は外出先から帰ってもとても暑くていられない、ということでは心身とも疲れがとれません。かといって、現在の家から引っ越すわけにはいきません。夏はエアコンで冷やし、冬は逆に強く暖房を効かさなければ快適な空間は維持できません。室内温度の調整に欠かせないのが窓なのです。
総務省統計局の資料によると、「総世帯」あたり家庭の電気使用料金は9,336円(2015年)がです。資源エネルギー庁のデータ(2009年)を見ると、そのうちエアコンが7.4%を占めています。ちなみに電気冷蔵庫は14.2%です。
統計データの年も違うので正確な比較はできませんが、計算上690円がエアコンの電気料金という計算になります。このデータは総世帯なので一人暮らしのお年寄りや学生も含まれます。育ち盛りの子どもたちがいる家庭は3~5倍以上になっているでしょう。
部屋が暑いと電気冷蔵庫の開け閉めも頻繁に行うようになります。